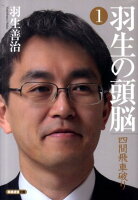今回は、進化した三間飛車をマスターできる一冊
「緩急自在の新戦法!三間飛車 藤井システム」
のレビューをしたいと思います。
この本は、四間飛車での居飛車穴熊対策として生まれた
「藤井システム」
を三間飛車で応用して進化させた戦法
「三間飛車 藤井システム」
を詳細に解説している本です。
居飛車穴熊への対策をメインにした
・対 穴熊編
から始まり、相手が穴熊をやめて変化してきた場合についても
・対 急戦編
・対 美濃編
としてしっかりカバーしているので
「これ1冊で現代の三間飛車について一通り必要なことを学べる」
という
「最新の三間飛車を学ぶならコレしかない!」
と言える内容になっています。
ここ数年の中でも特にオススメの一冊ですね。
どこがどうオススメなのか、一通り読んだ感想を書いていくので購入を迷っている方の参考になれば嬉しいです。
「△4三銀型の三間飛車」を掘り下げた1冊
この本の特徴は「三間飛車 藤井システムを中心とした△4三銀型の三間飛車」(下図)
1つに絞って紹介している所です。

三間飛車は
・△4二銀 型
・△4三銀 型
・△5三銀 型
など銀を広く使える自由度が魅力で
「左の銀をどう使うか」
で戦い方が変わる柔軟性が売りでもあるのになぜ1つに絞っているのかというと、早めの仕掛けを狙う藤井システムを使う場合、
「序盤早々に△4三銀と形を決めた三間飛車」
にする必要があるからです。
昔ながらの三間飛車を愛用している方にとっては
「早々に形を決めてしまうのはちょっともったいないような・・・」
と感じるかもしれません。
でも△4三銀型にしても
・急戦
・持久戦
の両方に対応できる充分な柔軟性がある上に
「振り飛車党なら1度は学ぶであろう従来の四間飛車の定跡と似た変化で戦える」
というメリットもあり、純粋な振り飛車党の方にはとっつきやすい内容になっています。
改めて「△4三銀型 三間飛車」の優秀さを見直す機会になるかもしれませんよ。
これから三間飛車を覚える方にとっては
「広く浅く定跡を覚えるより、実際に使う1つの形に絞って深く理解した方が効果的」
とも言えるので、
「△4三銀型 三間飛車」
という分かりやすい形1つをマスターできるこの本は最適な1冊になると思います。
三間飛車を使う側として、△4三銀型の
・対 穴熊
・対 急戦
・対 美濃
を一通り覚えれば特に問題はないので
「現代の三間飛車を学ぶならまずはこれ1冊でOK」
と自信を持ってオススメできます。
第1章 対 穴熊編 の感想
「三間飛車 藤井システム」の根幹となる対穴熊の基本から始まります。(下図)
まずは上図の元祖・藤井システムと似た変化に触れながら
・右桂の使い方
・玉の位置、囲い方
・端攻めの仕方
など、この戦法を指す上で大切なポイントを学べます。
上図の王道の形だけでなく、先手の駒組みに合わせて現代ならではの進化を遂げた攻め筋を「全5節」に渡って解説しています。
この5節に渡る「攻め筋」と「玉の囲い方」の解説は発想が柔軟で面白かったですね。
形にこだわらない自由な指し回しは参考になりました。
「居飛車とか振り飛車とか関係なく『1つの将棋』として捉える必要がある」
というのが現代の感覚なのかもしれません。
この章での個人的な収穫は「トマホーク(下図)」について知れたことでしょうか・・・

トマホークは従来の△7四歩 ~ △7三桂 ~ △8五桂 とは違い
「上図のように△9三桂 という素早い桂跳ねから居飛車穴熊の端攻めを狙う戦法」
なんですが、詳しいことを知らなかったので藤井システムと合わせて学べたのは大きかったですね。
・トマホークが有効な形
・そうでない形
を成功例と失敗例を交えて紹介しているので分かりやすかったです。
端攻めだけじゃなく左辺の捌きも見事で、これが決まれば爽快ですね。
対 穴熊で類似形に進んだ時はポイントを思い出しながら指せれば良い感じに攻め込める将棋になりそうです。
第2章 対 急戦編 の感想
この章では先手が▲3六歩(下図)から急戦で仕掛けてくる変化について解説しています。
上図からメジャーな攻め筋の
・▲3五歩 △同歩 ▲4六銀
・▲4六銀
・▲4六歩
への対策に始まり、
・上図とはちょっと違う形での仕掛け
・急戦と見せかけて玉を囲う変化
など、一通り△4三銀型で急戦に対応する手順が学べます。
急戦に対しては三間飛車で構えているのが活きる展開になりやすく、ここが元祖・藤井システムとは違うこの戦法の売りですね。
従来の「四間飛車 藤井システム」の知識がある人だと「三間飛車 藤井システム」と聞いて
「なんで△4五歩 で飛車と角が一気に働く四間飛車じゃなく三間飛車なんだろ?」
という疑問を持ったかもしれませんが、その疑問がこの章で解決すると思います。
・穴熊に組まれても互角以上に戦える
・急戦への対応もしやすい
というメリットによって見直されたのが分かりますから。
メジャーな四間飛車への急戦定跡と似た変化もあり、はるか昔に「羽生の頭脳1」で居飛車の急戦を学んだ私にとっては理解しやすい内容でした。
章の最後にまとめもあるので、対急戦へのコツを覚えれば怖いものはないですね。
安心して藤井システムを指せるようになると思います。
第3章 対 美濃編 の感想
この章では、急戦と穴熊の中間に位置するバランスのいい左美濃(下図)について解説しています。
ここから先手が
・銀冠 ~ 銀冠穴熊に組む変化
・急戦でくる変化
に対し、大きく分けると
・石田流に組む形
・藤井システムとして玉頭攻めを狙う形
での対策に分かれ、後手の指し方をポイントを抑えながら学べます。
石田流の指し方は、普通に石田流を指す上で必要な情報が手に入り、
「左美濃破り 石田流編」
という名前の本があったら第1章になりそうな充実した内容でした。
どういう風に指せばいいかのイメージを掴むには充分でしたから。
この章はこれから三間飛車を学ぶ人なら必読ですね。
ここまでの内容をしっかり頭に入れれば
「現代に必要な三間飛車の感覚」
がしっかり身について、これからの将棋を見る目も変わってくると思います。
雁木戦法も学ぶと幅が広がる
「三間飛車 藤井システム」の面白い所は、序盤 ~ 中盤の駆け引きとして「雁木戦法」
と連動している所です。
特に序盤の相手の囲い方次第では三間飛車にこだわらず、雁木として居飛車を選択することで優位に立てたりもしますから。
この本を読むとその意味が理解できると思うので、一通り読み終わったら雁木の本も1冊読んでおくといいかもしれません。
基礎から学ぶなら下記リンクの本はオススメです。
最後に
「緩急自在の新戦法!三間飛車 藤井システム」は、藤井システムを軸とした
「△4三銀型 三間飛車」
1つに絞り、三間飛車を指す上で必要な
・急戦
・左美濃
・穴熊
への対策をまとめて学べるので
「狭く深く三間飛車を研究して得意戦法にしたい」
という方には自信を持ってオススメできます。
以前のレビューで、初段の人に1冊だけ角換わりの本をオススメするなら
「神速!角換わり▲2五歩型」
ということを書いたんですが、
「もし初段くらいの人に1冊だけ振り飛車の本をオススメするならどれにする?」
と聞かれたら、迷わず今回紹介した
「緩急自在の新戦法!三間飛車 藤井システム」
をオススメしますね。
どちらの本も共通してるのは、
「これ1冊読んでおけばこの形の基本はもう大丈夫」
という分かりやすい所です。
序盤から終盤まで狭く深く1つの形について書かれているので分かりやすく実戦的ですし、本全体が流れで繋がっていて1冊で完結しているのが素晴らしすぎます。
「自分の勝ちパターン」
を見つけるならこういう風に1つを突き詰めるのが大切だと思うので、
「△4三銀型 三間飛車」
に興味を持った方は、せひこの本を手に取って得意戦法の1つにしてください。