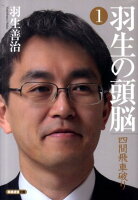今回は、きのあ将棋の「郷谷さん(上級)」が四間飛車をやってきた時にけっこう見かける
端攻めへの対策(下図)

について書いてみたいと思います。
私の実戦譜を元にAperyで検討した手を紹介するので、もし同じことをやられた時の対策としてお使いください。
斜め棒銀に対する▲9七香 が始まり
先手が「郷谷さん」、後手が「私」です。
上図は郷谷さんの四間飛車に対して斜め棒銀で攻めようとした所です。
昔懐かしい急戦定跡ですね。
ここまでの手順がよく分からない方は「羽生の頭脳1」を読むといいですよ。
次に△7五歩 からの仕掛けを狙っている△6四銀 に対し、次の一手を指してきたら端攻めを狙ってくることがあります。
上図以下、▲9七香(下図)

角筋を避けて香車を上がるのはよくある手ですね。
ここで▲9八香 と1つだけ上がった時は普通の定跡に進みやすいですが、▲9七香 の場合は後々▲9八飛 から端攻めを狙ってくる傾向があります。
とは言ってもまだ分からないので、とりあえず普通に仕掛けて様子を見ます。
上図以下、△7五歩 ▲7八飛(下図)

▲7八飛 と攻められている筋に飛車を回る定番の一手で受けてきました。
この手は振り飛車を指すなら大切な感覚なので覚えておくといいですよ。
上図以下、△7六歩 ▲同銀 △7五歩(下図)

△7五歩 の所では
・△7二飛
・△8六歩 ▲同歩 △7二飛
のような一気に決戦に持ち込む手もありますが、個人的には△7五歩 と押さえてジックリいく手が好きです。
上図以下、▲6七銀 △7三銀引 ▲5九角 △7四銀(下図)

7筋の位を確保してゆっくりした展開になりました。
ここから端攻めを含みにした手順で揺さぶられます。
上図以下、▲8八飛 △6四歩 ▲9五歩(下図)

▲8八飛 ではダイレクトに▲9八飛 と回る手を指してくることもあります。
どちらかと言えば▲9八飛 の方が怖いので今回は助けられた感がありますね。
そして端から仕掛ける▲9五歩 で▲9七香 と上がった手と繋がってきました。
実戦は△9五同歩 と取ったんですが、それはやや疑問だったようでAperyは違う手を推奨していました。
まずはApery推奨の手順から紹介します。
▲8八飛 をとがめるAperyの手順

上図の仕掛けには▲8八飛 の欠点を突く仕掛けが成立していました。
上図以下、△6五歩 ▲5六銀 △6六歩(下図)

角筋を活かして普通に△6五歩 から飛車を狙って後手優勢だったようです。
上図以下、▲9八飛 △8六歩 ▲同歩 △8七歩(下図)

この△8七歩 の垂らしが強烈ですね。
上図以下、▲6三歩 △同銀上 ▲6四歩 △同銀 ▲9六香(下図)

▲9六香 で飛車の逃げ場所を作りましたがシンプルに攻めて後手優勢です。
上図以下、△8八歩成 ▲9七飛 △7八と ▲9四歩 △6九と(下図)

△8八歩成 を▲同飛 と取ると△6七歩成 の飛車取りが強烈なので取れません。
取れない「と金」が△6九と まで進めば盤石ですね。
以下、▲7七角 と逃げれば△7六歩 ですし、▲9三歩成 も△8四飛 とかわせば大丈夫です。
もし▲8八飛 としてきた場合にはこの仕掛けで圧倒してください。
本題となる端攻めの受け方
局面を戻します。
上図は先手が▲9五歩 と端から仕掛けてきた所です。
ここで△6五歩 と仕掛ければ角筋を活かした攻めで後手優勢でしたが、実戦は△9五同歩(下図)と取りました。

平凡に対応すると指しがちな一手ですよね。
でも、こうなると端攻めに勢いがつくので気をつけなければいけません。
まずは実戦譜の前にApery推奨の手順をご覧ください。
上図以下、▲9八飛 △8四飛(下図)

シンプルに飛車を浮いて端攻めを緩和するのがいいみたいです。
上図以下、▲9五香 △9三歩(下図)

これで一方的に攻め込まれることはありません。
上図以下、▲9三同香成 △同香 ▲9四歩 △同香 ▲9五歩 △6五歩(下図)

もし上記の手順のように強引に攻めてきても大丈夫です。
上図以下、▲9四歩 △6六歩 ▲5六銀 △9二歩(下図)

しっかり△9二歩 と受けておけば問題ありません。
▲9五歩 の仕掛けを△同歩 と取ってしまった場合はこの手順で受けてください。
私が実戦で指した手を紹介します
ここからは私の実戦譜を紹介します。端攻め対策としてはここまでに書いてきたAperyの手順でOKなので、お暇な方のみお付き合いください。
▲9八飛 に対してAperyは△8四飛 と浮く手を推奨していましたが、私が指したのは△8六歩(下図)でした。

「とりあえず角筋を止めておきたい」
という一手ですね。
もし▲8六同角 なら、そこで△8四飛 と浮けばそこまで悪くありません。
まぁ実戦では△8四飛 なんて考えてませんでしたけど・・・
「歩で取ってくれ」
と願っていただけでした。
実戦はその願いが叶って▲8六同歩(下図)となったので助かった感じですね。

ここからそこまで悪手ではないけど筋が悪そうな一手で端の受けに回りました。
上図以下、△8三銀 ▲4七金 △9四銀(下図)

過去に端を放置して攻めにいって負けたのもあり、
「ここは我慢して受けなければいけない」
というのが頭にあったので攻めに使いたい銀を受けに使ってガッチリ受けました。
ここからゆっくりじっくり抑え込みの方針で指します。
上図以下、▲7八飛 △7二飛(下図)

後手からは特に速い攻めもないので先手の手に対応していきます。
上図以下、▲2六角 △6三銀 ▲5六歩 △7四銀(下図)

7筋の位を確保して順調だと思いました。
上図以下、▲9八飛 △8二飛 ▲7一角成 △8六飛(下図)

ただ、受けに回りっぱなしなのが性に合わないのか△8二飛 から角成りを許して飛車をさばきに出る暴挙へ・・・
そこまで悪手ではありませんが、方針を一貫しないのはけっこう危険ですね。
上図以下、▲7八銀 △7六歩 ▲8二歩 △8七歩(下図)

反撃を受けないように△7六歩 ~ △8七歩 と丁寧に指し、どうにか形になりました。
上図以下、▲8一歩成 △8八歩成 ▲9一と △7八と(下図)

ここで飛車を取らずに△7八と と銀を取るのが大切な一手です。
もし△9八と と飛車を取ると▲8七香(下図)で飛車が詰んで形勢が戻っちゃいますから。

いつもならこの手を食らっていただろうけど気付けてよかったです。
△7八と 以下、▲同飛 △8九飛成 ▲7六飛 △8五銀右(下図)

端を受けるだけで終わりそうだった銀も働いて抑え込みも成功しました。
ここから色々あって迎えた最後の詰みを実戦詰将棋として出題して終わります。
実戦詰将棋の出題

上図は先手玉を追い詰めた局面です。
実戦は△2五桂 と打って郷谷さんの投了となったんですが、ここでは詰みがありました。
実戦詰将棋として出題するのでお時間のある方は解いてみてください。
いくつか詰み筋があるみたいなんですが、個人的に
「この手は他でも使えそう」
と思った手順を答えとして解説します。
答えは数行下に書くので答えが浮かんだら進んでください。
では答えです。
上図以下、△2六桂(下図)

と打つのが分かりやすい詰み手順だと思います。
・▲同銀 なら△3八竜
・▲同歩 なら△3八竜 ~ △2七金
の詰みなので▲2六同馬(下図)と取りますが・・・

上図以下、△2八金 ▲同銀 △同銀成 ▲同玉(下図)

桂捨ての効果で馬が2六の地点を塞いでいるので簡単になってますね。
上図以下、△3九角成 ▲3七玉 △3八竜(下図)

までの詰みです。
上に逃げられるとめんどくさい感じがありましたが、それを防ぐ桂打ちは使える手筋だと思います。
知っておいて損はない手だと思ったので紹介してみました。
もし実戦で似た形になった時に桂捨ての筋が浮かんでもらえたら幸いです。
最後に
郷谷さん(上級)が四間飛車に振った時にやってくる端攻めの対策を紹介してみました。Aperyが推奨していた△8四飛(下図)のように軽く浮いて受けるのが無難かと思います。

郷谷さんが▲9七香 と上がった時は今回の手順を思い出してキッチリ勝ち切ってください。