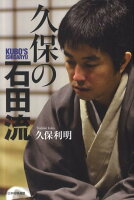今回は、早石田の急戦を中心に一通り石田流の指し方が学べる本
「久保の石田流」
のレビューをしたいと思います。
この本は、現代の早石田を学ぶ上で欠かせない
・早石田 定跡
・鈴木流 急戦
・久保流 急戦
といった序盤から良さを求めて動く急戦定跡、
への従来とは違う指し方、
・△3二飛 戦法
・久保新手
などの新しい石田流までを一通り学ぶことができる本です。
解説の中では「久保の石田流」のタイトル通り
久保先生ならではの「さばき」のコツ
についても少し触れられる内容になっているので
「久保将棋のファンなら買い」
な内容になっています。
この記事では、ザっと内容に触れながら感想やオススメポイントを書いていくので、購入を考えている方の参考になれば嬉しいです。
- 「升田式石田流」の基本から学べる
- 急戦定跡を「早石田定跡」の基礎から学べる
- いきなり仕掛ける「鈴木流 急戦」
- 進化した早石田定跡「久保流 急戦」
- 「棒金」への久保新手
- 「左美濃」相手のさばき
- 「穴熊」相手のさばき
- 4手目△5四歩
- 後手の石田流
- 2手目△3二飛 戦法
- 最新の石田流
- 最後に
「升田式石田流」の基本から学べる
急戦定跡に入る前に早石田の基本となる「升田式石田流」(下図)

について、基礎から現代の課題まで学べます。
上図から、△8六歩 ▲同歩 △同飛(下図)

と飛車先の歩交換にくる対策を知らないとけっこう困る手や、升田式では定番の
・▲7七桂型(下図)

・▲7七銀型(下図)

について基本的な定跡本より踏み込んだ手順を知ることができます。
これらの基本を踏まえた上で現れた新しい指し方にも触れているので、早石田を本格的に学ぶなら読まない手はありません。
個人的には上記の
「▲7六飛 と浮く前に飛車先の歩交換に来られた時の手順」
を改めて知れたのが参考になりました。
升田式石田流について古い定跡で止まっている方には、おさらいも含めて読む価値があると思いますよ。
急戦定跡を「早石田定跡」の基礎から学べる
・鈴木流 急戦・久保流 急戦
といった現代の急戦を知る前に抑えておかなければいけない
「早石田定跡」(下図)

の解説から急戦定跡の説明が始まるのでポイントを理解しやすいです。
上図以下、△7四同歩 ▲2二角成 △同銀 ▲5五角(下図)

という玉の囲いもそこそこにいきなり仕掛けるハメ手風の手順を食らって困った居飛車党の方もいますよね?
「△7四同歩 と取った手が悪い」
というのは定説ですが、実は上図の展開でも頑張れば互角にまで持っていけるみたいです。
この攻め筋や受け方を知ることが現代の急戦への始まりなので、もしこの手への正しい指し方を知らないなら読む価値がありますよ。
いきなり仕掛ける「鈴木流 急戦」
「早石田定跡」の手順を踏まえたらようやく現代の急戦へと入ります。まずは、鈴木大介八段(当時)が発見した
「鈴木流 急戦」(下図)

についての基本的な指し方から・・・
いきなり仕掛けるこの手は指す方も指される方も怖いですね。
「角交換から△6五角(下図)の角打ちがあるから無理」

とされていた仕掛けがなぜ成立したのか。
居飛車党で早石田を受けて立つ人には避けられない変化になりますし、お互いに△6五角 からの手順をしっかり指せないとあっという間に劣勢になるので、この本で基本的な手順を抑えておくといいですね。
進化した早石田定跡「久保流 急戦」
基礎となる「早石田定跡」から始まり、久保先生が「鈴木流 急戦」に刺激を受けて色々と研究して生まれた「久保流 急戦」(下図)

までの解説で、進化してきた早石田の急戦定跡の流れを理解できます。
上図を見ると
「さっきの早石田定跡じゃない?」
と思うかもしれませんが、ここから後手が△7二金(下図)と正しく受けた所で久保先生の工夫した新手が現れます。

これがこの本の売りだと思うので、どんな新手かは本書を買ってからのお楽しみということで・・・
久保先生らしい「さばき」を狙った新手とそこからの手順は一見の価値がありますよ。
「棒金」への久保新手
急戦の解説の後は、オーソドックスな石田流の定跡に移ります。ますは「棒金」(下図)から・・・

後手が金で抑え込みにくる戦法ですが、この手に対して定番だった一手が通用しなくなったことで生まれた
「久保新手」
による解説が書かれています。
・従来の手順が通用しなくなった森内新手
・久保新手による「さばき」
を知ることで「棒金」への指し方が大きく進歩しますね。
ここで解説されるキレイにさばく手順は振り飛車党なら感動すると思いますよ。
「左美濃」相手のさばき
次は後手が「左美濃」(下図)に組んだ場合の解説に進みます。
上図から△8五歩 ▲7六飛 △6五歩 の急戦にくる変化と、お互いに囲い合う持久戦での指し方を学べます。
急戦も持久戦も、実戦を踏まえて見つかった「さばき」の手順が見事でした。
「久保の石田流」のタイトル通り、久保将棋の魅力を存分に味わえます。
特に持久戦での攻め筋は石田流の理想形とも言えるキレイな手順なので一見の価値ありです。
「穴熊」相手のさばき
左美濃の次は「穴熊」(下図)への解説です。
対 穴熊の解説はサラッとですが、ここでも久保先生らしい石田流の見事なさばきを見ることができます。
穴熊への効果的な一手を知ることで戦いやすさが変わってくると思います。
4手目△5四歩
一通りメジャーな戦法の解説の次は早石田に対する後手の工夫「4手目△5四歩」(下図)

への指し方の解説です。
・シンプルに▲7八飛 と振った場合の角交換から△4五角 の変化
・△5四歩 の狙い
についてサラッと解説されていて、先手が上手くいった場合の一例として「石田流本組み」でのキレイな攻めを見ることができます。
理想形に組めた時の攻め筋がよく分かってない方には役立つ情報ですね。
後手の石田流
後手番で石田流を指すにはどうすればいいかの解説もあります。先手に知識がなければ下図のように普通に早石田に振ることができるんですが・・・

実は後手番では△3五歩(下図)の所で先手からいくつかの対策があり、そう簡単にはいきません。

この先手の対策は指されてみないと気付かないと思うので、後手番でも早石田を狙うなら知っておかなければいけない変化になります。
早石田が「先手番の戦法」と言われている理由を知れる貴重な情報ですね。
2手目△3二飛 戦法
先ほどの先手の工夫により「後手番ですんなり早石田に組むのは難しい?」
という感じになった所で突如生まれた新戦法
「2手目△3二飛 戦法」(下図)

の解説があり、
「後手番だったらどうすればいいのやら・・・」
という悩みを持った方へ救いの手を差し伸べてくれます。
一見 ▲2六歩 から角頭を狙われてダメそうに見えますが、乱戦模様の反撃でどうにか大丈夫という発見がされました。
序盤の基本を学べば後手番でも石田流を狙う将棋を指せるようになりますよ。
最新の石田流
最後は局面を下図の最初に戻し、色々あった急戦策を経て見直された最新の手順に触れています。
色々あった末にこの局面から
江戸時代の手が見直されたり・・・
ちょっとした手順の違いでまた違った早石田の将棋になったり・・・
将棋の奥深さが分かる面白さがありますね。
ここでも「久保新手」と呼ばれる手があり、いかに久保先生がこの戦法の研究と貢献をしているかが分かります。
どんな新手かは本書を買ってからのお楽しみということで伏せておきますね。
最後に
現代の石田流について学ぶなら・鈴木流 急戦
・久保流 急戦
・棒金の森内新手
・棒金の久保新手
・後手 早石田への対策
など、早石田から始まる石田流を指す上で必要な知識が得られる
「久保の石田流」
は最適な一冊になります。
久保先生ならではの「さばき」を重視した解説で学べるので振り飛車党の方には得るものが大きいと思いますよ。
「過去の戦法」から「現代の戦法」
に至るまでの流れがまとまった
「早石田の歴史書」
のような感じでも読めるので
「ちょっと早石田を知識として入れておこうかな・・・」
と思っている方にもオススメです。
早石田の定跡やコツを一通り学びたい方はぜひ読んでみてください。